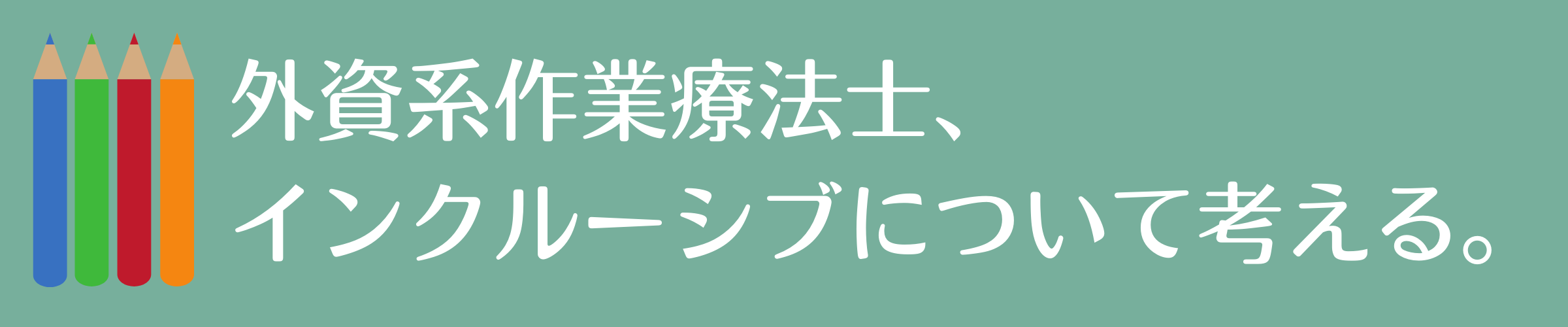こんにちは。
外資系の療育機関で子どものサポートをしている、作業療法士のゆこです。
今回は「靴をはく」ということについて。
とくに左右の靴の認識について。
小さい子どもは、よく靴を左右間違えて履こうとすることがありますよね。
本気で分かっていなくてそうする子もいれば、反抗心なのか面白いのかわざとそうする子も。
間違えて履いてしまった子どもに対して、
「お母さんが怒るからちゃんと履いて」とか「恥ずかしいからやめて」などと声をかけているのを聞きました。
私がこういう場面に出会ったときは、
①自分で気づくかどうか待つ(足の違和感で気づいて自分で直す場合あり)
②間違えて履いていたら、
「あなたがいいなら私はいいけど、たぶん反対だと思うし、気持ち悪くない?」と声をかける
という対応をするのが、ここ数年のテッパンになっています。
これがいいかどうかはわからないですが…
子どもが自分で気づかないなら、その理由が。
反対に履くのを好むのであれば、その理由があるんだと思っています。
そもそも「靴」の役割とは
靴には大きく3つの役割があるそうです。
①保護:足を暑さや寒さ、衝撃や摩擦などによるけがから守る働き
②補助:足の動作を助けたり、疲労を軽減するための働き
③装飾:足元を美しく見せるファッションの一部としての働き
ちなみにサンダルは農耕民族、つま先を覆う靴は狩猟民族がルーツだそう。
靴が生まれた第一の目的は「保護」なんですね。
なので、とりあえず左右間違っていたとしても両足に履いていたとすれば、靴の第一の機能は果たしているわけです。
少なくとも足は覆われているわけなので。
靴の左右があるのは「補助」のため。
さらに機能性を持たせるために、足の左右の形に合わせて靴が作られ、様々なアレンジがされてきたわけです。
靴の左右を識別するには
①見た目
②履き心地
この二つが大きな要素だと思います。
「見た目」で判別するためには、形を認識する力が育っていることが大切。
たいていの靴は、左右反転させれば同じ形。
十分に視覚認知能力が発達していなければ「同じ」と認識してしまう可能性も大いにあります。
まだベルトとかがついていればいいですが、よくある体育館シューズの左右を見分けるのは至難の技。
そして、さらに「自分の足の形」との照合も必要になります。
足の細かい形ではなく、輪郭だけをとらえて、照合する。
何て難しいことを人間は自動的にやっているんでしょう!
次の「履き心地」ですが、左右反対に履くとまあ「気持ち悪い」と感じるのが一般的ではないでしょうか。
歩きにくい、締め付けが変。
誰かと話しながらなんとなく足を突っ込んだら間違えていて、感覚で気づくということはあると思います。
何なら、履き続けている人の足に合わせて靴の形が変わってくるので、人の靴を履くと「なんか違う」となることもあるのでは。
これに関しては「足の感覚」が育っていることが大切。
足を触って、指を動かして、足の形と動きの「地図」が出来上がっている必要があります。
靴を間違えずに履くために
よくあるのは、上履きとかだと中敷に左右を正しく置くと完成する絵を足り描いたりすること。
右足用の靴だけに何か目印をつけたり。
「見た目を間違える」場合にはとても有効だと思います。
同時に、形の認識につながるようなトレーニングをしてみてもいいかも。ひっくりかえった図形を見つけるとか。
左右の識別を高めるような遊びも有効だと思います。
間違えても気にしていない場合は、足の感覚を育てるところから。
もちろん裸足で活動することもよい刺激になると思います。
坂道でしっかり足を踏ん張ったり、クライミングのように足しっかり刺激が入るようなことだったり。
お風呂で足を指一本ずつしっかり洗ってみたり。
周りの大人が先回りして間違いを正してしまったり、間違いが起きないような状況を先につくるのはもったいない。
靴のはたらきの2つ目、補助の役割について、正しく履くとどんないいことがあるのか話すのもよいと思います。
子どもが靴を反対に履いていて恥ずかしい、と思うのは大人側の目線。
ぜひ、まず、「なぜ」そうするのかを考えていただきたいです。
そしてそれを見る周りの大人は、子どもの成長を暖かく見守れる存在でありたいなと思うわけです。
おわり。
以上、読んでくださりありがとうございました!
●ランキングに参加しています。応援いただけるとうれしいです。
![]()
![]()
![]()
にほんブログ村