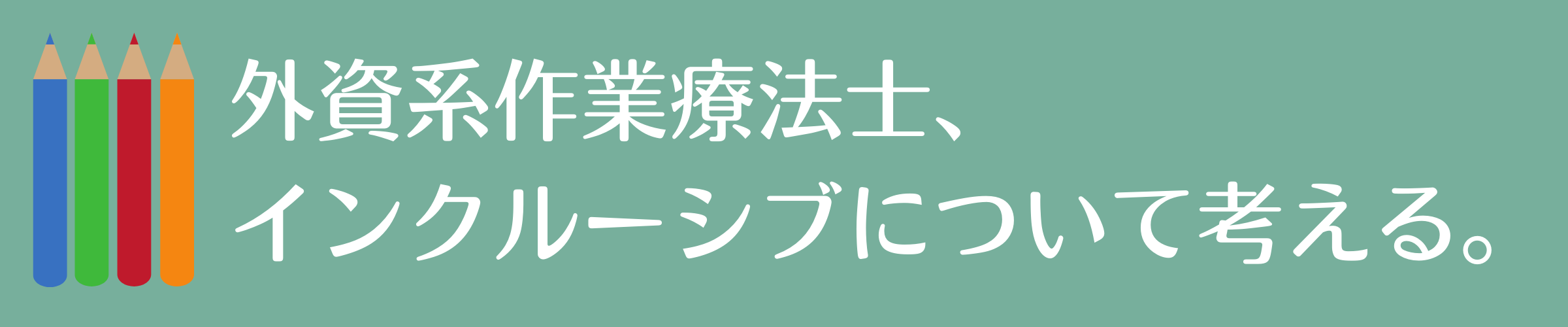こんにちは。
外資系の療育機関で子どものサポートをしている、作業療法士のゆこです。
7月に短期留学に行き、うち3週間をボランティア留学という名目で現地のデイケアに潜入してきました。
前回は、デイケアの基本情報などなど。こちらからどうぞ。
今回は、作業療法士として見たデイケアについての感想。
日本とカナダ、子どもたちの違い
子どもは子ども、変わらないだろうと思っていましたが、少し違いました。
言語化するのはすごく難しいのですが、一言でいうと「自立している」。カナダの方がね。
一番小さくてもう少しで3歳の子がいたのですが、もうしっかりおしゃべりしていて、
やりたいこともはっきりしていて、だれかに何か取られたらちゃんと主張をする。
自分で言っても聞いてもらえない、解決できないならちゃんと先生に言う。
理由も言う。状況をちゃんと説明する。
ひとりでもやりたい遊びをするし、誘いたければ誘う。
誘われた側も、やりたくなければ断る。
そういったことがすごく低年齢のうちから大切にされているなということを感じました。
ボランティアとしての心構え的なガイドラインにも、大人が必要以上に介入しない、
本人の意思決定を大事にしてほしいということが書かれていました。
先生の関わり方
基本的に、自立を促す、というのがメインになっていることを感じました。
そして、言語でのやりとりが主だなということも感じました。
何か問題が起これば、なぜそれが起きたのか子どもに説明させるし、やりたいことや、手助けを求める際も「何がしたいの?」「何か手伝いがいる?」などさりげなく聞いて、表出は本人からさせる。
日本と違いがあるか?と言われると、そこまで大きな差はないのかな、とは思います。
何でもやってあげたくなっちゃう系の先生、先回りしてしまう先生というのは日本の方が多いのかも。
Early Learning Frameworkについて
園の先生とカナダの教育のシステムについて少し話す機会があったときに、バンクーバーの位置するブリティッシュコロンビア州には、”Early Learning Framework”という、幼児教育に関するガイドラインがあることを聞きました。
訪れた園は、どちらかというと歴史のある園で、古いタイプの教育システムの中にまだいると言っていましたが、州ではこのガイドラインに基づいて教育を提供していくように言われていると聞きました。
残念ながら、もちろん全部英語なので(笑)全然読み切れていなくて、最初のページどまりで、このガイドラインが幼児教育について何を言っているのかまではまだ理解できていないのですが、こういうガイドラインがあることで先生たちが同じ理解をもって教育に参加できるのは良いことな気もします。
100ページ以上ある資料なので、少しずつ読んでみようと思います。
いわゆる「気になる子」について
特別支援教育のシステムについて詳しく聞けなかったので残念だったのですが、正直、そういった子どもたちに対する対応が良かったか、と言われると、そうではなかったと感じています。
20人ちょっとの子どもたちの中で「気になるな」という子は2人。
どこにいっても10%なのかなあ。
1人は、少し知的な部分で遅れがあるのかも?と思わせるような、ことばが少し遅い、説明がうまくできない、他の子どもたちとトラブルをよく起こして真っ先に泣いてしまう子。
もう一人は、いわゆるスペクトラムの子では?という印象を受けた、偏食あり、先生の言葉まねをよくする、自分のぬいぐるみにはこだわりを持っている子。
異年齢の子どもたちが多い中で、彼らに個別に適切なかかわりがなされていたか?と言われると、うーん…という感じでした。
1人目の子は、他の子たちにいいように用いられてた感もあって、少しかわいそうだった。
学校になるとまたシステムが変わるのかもしれないし、1か所の園を見ただけではわからないことばかりですが、専門職が介入する余地はいっぱいあるなあと思いました。プログラムの組み立てとか、部屋の環境設定とかに関しても。
結論
国によって何がいいとか悪いとかはない!(究極の結論)
もっとスタッフ側もインクルーシブになって、いろんな目線で子どもたちの育ちを支援していけるようになればなあ。
以上、読んでくださりありがとうございました!
●ランキングに参加しています。応援いただけるとうれしいです。
![]()
![]()
![]()
にほんブログ村